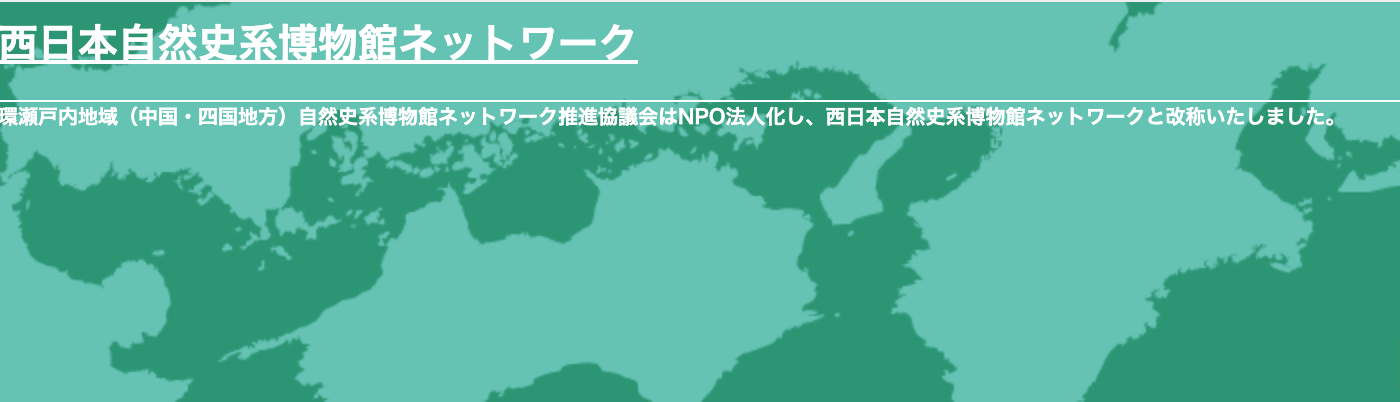西日本自然史系博物館ネットワークはInnovateMuseum事業の一環として以下の実習を開催します。定員16名と限られますが、どうぞご参加ください。
「3Dプリンタで広がる触察モデルの世界」
~視覚障害者支援のためのモデル制作を体得する2日間~
この度、3D4SDGsのみなさんに大阪に出張いただき、博物館関係者のみなさんを対象に、視覚障害者向けの触察モデルを3Dプリンタを活用して作成する実践型プログラムを開催いたします。
視覚障害を持つ方々にとって、触察モデルは情報や理解を深める重要な手段です。本イベントでは、最新の3Dプリンタ技術を使用し、誰でも簡単に触察モデルを制作できるスキルを学んでいただきます。
※この講習は、文化庁補助金事業Innovate Museumの助成により行います。
イベント詳細
日程:1日目:2月4日(火)10:00~17:00、2日目:2月5日(水)10:00~16:30
会場:大阪市立自然史博物館実習室(大阪市東住吉区長居公園1-23)
対象者:博物館関係者および博物館のまわりで展示や普及教育活動をしている人で、視覚障害者の博物館体験を支援したい人
プログラム内容:
Day 1: 3Dプリントの基礎と実践
午前:3Dプリントの概要説明とプリンタ操作体験
3Dプリントの基本原理を学び、QRコードを使った簡単なプリント体験を行います。
プリントに使用する「Bambu Studio」の基本機能を学び、色分けやスライスの方法を実践します。
午後:3Dスキャン技術と触察モデルの作成
スキャンアプリを使った3Dスキャンの基礎を体験。
オンラインで触察モデルの検索・ダウンロード方法を学び、スライサーソフトを活用して3Dプリントを行います。
Day 2: 3Dモデリングとデータ処理
午前:Tinkercadでの3Dモデリング
ペンシルホルダーやネームプレート、地図をモチーフにしたキーホルダーを設計します。
設計したデータをスライスし、3Dプリントを実践します。
午後:地図データからのモデル作成とカスタマイズ
終了セッション:感想の共有と次のステップの案内
参加者全員で成果物を共有し、次の学習・実践に繋がる情報を提供します。
講師紹介:
・林 園子 氏(ICTリハビリテーション研究会 代表理事・ファブラボ品川ディレクター・作業療法士)
・濱中 直樹 氏(ICTリハビリテーション研究会 理事・ファブラボ品川ファウンダー・一級建築士)
・南谷 和範 氏(大学入試センター 研究開発部試験基盤設計研究部門 教授)
・渡辺 哲也 氏(新潟大学工学部 教授)
主催:NPO法人西日本自然史系博物館ネットワーク、大阪市立自然史博物館
注意事項:PC、スマートフォン、メールアドレス(必要なアカウント作成用)をご準備ください。
PCは以下のシステム要件をご確認ください。
オペレーティングシステム:Windows 10 以降 Mac OS X v10.15 以降 Linux Ubuntu 20.02 以降、または Fedora 36 以降
プロセッサ:Intel® Core 2 または AMD Athlon® 64 プロセッサ、2 GHz 以上
グラフィックス:OpenGL 2.0 に対応したシステム
メモリ(RAM):最低要件:4 GB
ハードディスク空き容量:2.0 GB 以上の空き容量
お申し込み方法:下記メールアドレスまで、氏名、所属、返信用メールアドレスを記入して、お申し込み下さい。
y-ishii@omnh.jp (大阪市立自然史博物館 石井陽子)
定員:16名(先着順)
申込締切:1月26日(日)
お問い合わせ y-ishii@omnh.jp (大阪市立自然史博物館 石井陽子)