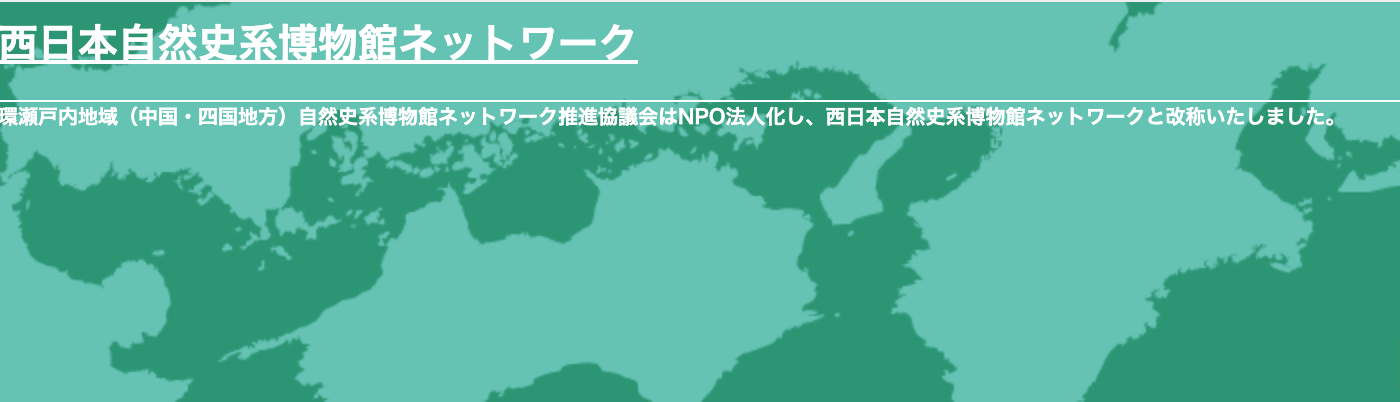ようやくしのぎやすい時節となりましたが、皆様におかれましては益々ご活躍のことと思います。大阪府高槻市にある芥川緑地資料館(あくあぴあ芥 川)の花﨑といいます。
このたび、NPO法人西日本自然史系博物館ネットワークとの共催で、博物館スタッフのための技術講座を開催するはこびとなりました。今回は、当 資料館(あくあぴあ芥川)にて、プラスティック封入標本作成講座、作成技術の習得と、封入標本の活用に関するワークショップを開催いたします。
皆様のご参加をお待ちしております。
また、この講座を関係者の方々に御周知していただければ幸いです。
======================================================================
◆◇博物館スタッフのための技術講座 プラスティック封入標本作成講座◇◆
NPO法人西日本自然史系博物館ネットワーク
博物館学芸員技術講習会事務局 三橋弘宗
1.日時:2010年11月29日(月) 10:30〜17:00
2.場所:芥川緑地資料館 (あくあぴあ芥川)
〒569-1042 大阪府高槻市南平台5−59−1
TEL:072-692-5041 FAX:072-692-7864
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/66/4903.html
E-mail: info★aquapia.net ★を@に
3.主催:NPO法人西日本自然史系博物館ネットワーク・芥川緑地資料館
4.趣旨/呼びかけ文
プラスティックの中に標本を埋め込んで作製する封入標本は、標本を手にとり、様々な角度から観察することができるため、博物館の展示や自然観察 会のツールとして近年普及しております。かつて封入標本は高価でかつ作製が困難なものでしたが、最近になって個人でも特別な道具を使うことなく、 封入標本を美しく仕上げるノウハウが確立されたことで、学校教育や博物館のセミナーといった普及現場での活用が可能となりました。そこで、この講 座では博物館学芸員・スタッフや自然観察指導者を対象として、封入標本の作製技術を習得して頂き、各館の博物館活動に活用していただくことを目的 とします。
5.参加対象
博物館学芸員、博物館スタッフ、自然観察指導者、ビジターセンター等関連施設スタッフ(NPO法人西日本自然史系博物館ネットワークの会員以外 の方も可能ですが、応募者多数の場合は会員の方を優先いたします)
6.講師
三橋弘宗(兵庫県立人と自然の博物館:主任研究員)
花﨑勝司(芥川緑地資料館:主任研究員)
7.参加料金
一人1500円(材料代含む)
8.募集人数
15名 (応募多数の場合は会員の方を優先させていただきます)
9.講座の概要
11月29日(月)
10:00〜 受付開始
10:30〜 封入標本の作製の作り方解説
11:00〜 封入標本作成実習
標本への樹脂流し込み
標本の研磨練習 (既に硬化させたものを用意しております)
17:00 終了
※途中で昼食になりますが、当館周辺には飲食店やコンビ二などがありません。昼食は各自ご持参くださるようお願いします。
18:00頃〜 懇親会
※JR高槻駅周辺で開催予定です。
10.申し込み
参加を希望されます方は、下記申込フォームに御記入いただき、申込締め切り日までにFAX,もしくはE-mailのいずれかの方法で下記まで御 連絡下さい。
◆申込先
芥川緑地資料館 (あくあぴあ芥川) 担当:花﨑勝司(ハナザキカツジ)
〒569-1042 大阪府高槻市南平台5−59−1
TEL:072-692-5041 FAX:072-692-7864
E-mail: info★aquapia.net ★を@に
=================<<申込フォーム>>============================
氏名:
所属:
NPO法人西日本自然系博物館ネットワークの会員ですか?
個人会員である ・ 博物館会員である ・ 会員ではない
(該当するものに○をつけてください)
懇親会: 参加する ・ 参加しない
(どちらかに○をつけてください)
連絡先(所属先・自宅)どちらかに○をつけてください
住所:〒
電話:
FAX:
E-mail:
=============================================================
11.申込み締切り
2010年11月15日(月)(必着)
12.その他
●当日、封入する標本につきましては主催者で用意しますが、参加者の皆様が封入してみたい標本がありましたら御持参ください。持参して頂く標本に ついては、以下の条件を満たしていただくようお願いします。
・シリカゲル等と一緒に密封し、完全に脱水されていること
・液浸標本の場合には、99%エタノールを用いて水分が完全に置換されていること。
標本に関して何かご質問等がございましたら、三橋まで事前にご相談ください
(電子メール:hiromune★hitohaku.jp ★を@に)。
●その他不明な点などございましたら、花﨑まで御連絡下さい。