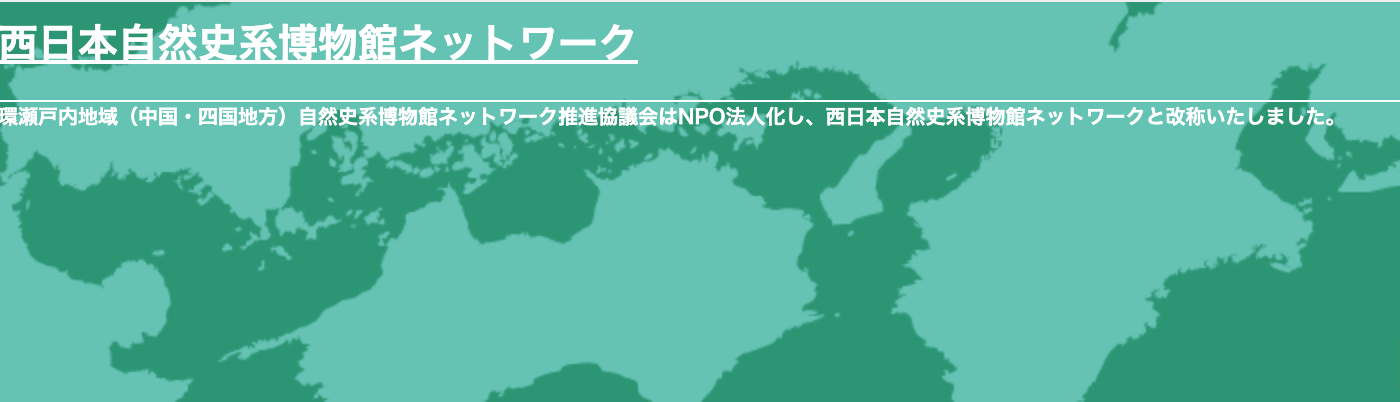図書館総合展での博物館関連イベント
11月5−7日 パシフィコ横浜で開催される #図書館総合展 で「越境・Openのための逗留地」なるスペースで博物館とオープンデータに関連するミニ集会を色々展開します。 – 図書館総合展2024 ブース&フォーラム https://openglam.github.io/LF2024.html…
博物館関係では
11月5日
13時から「デジタルな社会の博物館、国際動向をにらみながら」としてSPNHC、TDWGの総括
オンライン参加の方:https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYoduytrTMjGtP6cfzMkaZgcJADO-WhmkXT
14時から「博物館のOpen化、進めるには何が足りない?CivicTechにできることは?」なんてのをやります。
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqdeyhrDguGdPvN8_pHZmgV5oz4yP7ccFH
16時からは 「小さいとこ図書館総合展に集まろうジャン」が開催
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcqceGrqT4jHdQQiJGgcb4X4_EK9Ne2SNx_
11月6日
16時から「図書館・博物館の動きを国際的視点から眺めてみる」として豊田恭子さん(東京農業大学「闘う図書館 アメリカのライブラリアンシップ」「アメリカ大統領と大統領図書館」)・和気尚美さん(慶應義塾大学「デンマーク式 生涯学習社会の仕組み」ほか)と語らってみます。
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlcOyspjwiHdcCTBHRlCA5Dy8nXGz66r8X
11月7日(最終日)
10時30分からはフォーラム「図書館・博物館のOpen化を推し進めるために」があります。
各イベントにはバーチャル参加ができるものもあります。詳しくは各リンクから
https://www.libraryfair.jp/forum/2024/1066-1
ブースイベントの詳細はこちらから。