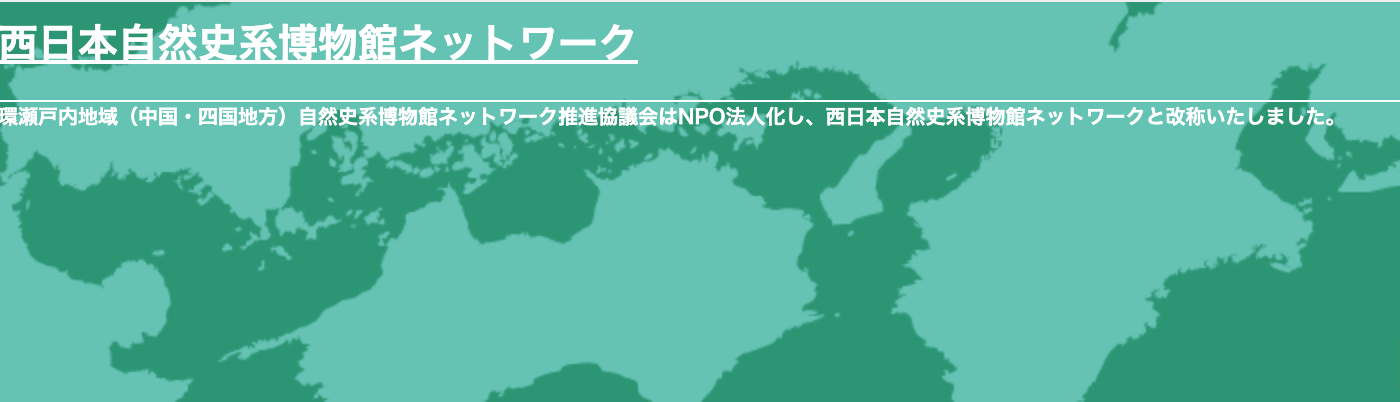「100均☆自然史グッズ」のワークショップが展示として公開されました。
さる2012年9月21日に開催された西日本自然史系博物館ネットワークのワークショップ 「どこまで使える 100円グッズ」の一環として作成された展示が、大阪市立自然史博物館2F イベントスペースにて公開されています。11月10−11日の自然史フェスティバルまでの約1月半、公開されています。ワークショップに興味があっても参加できなかった方々もどうぞご来場ください。
ミニ企画展「100均☆自然史グッズ」
本格的な観察道具で「形から入る」のもいいけれど、「100均」ショップで売っている道具で、気軽に自然観察に活用してみるのはいかが?
いいとこも、わるいところもあるけれど、ちょっとした工夫で活用の幅は広がります。
西日本自然史系博物館ネットワークではこれまで3回にわたって100均グッズを活用する研究会を開いて来ました。今回の展示は、その集大成として (1)観察 (2)採集 (3)標本 の3テーマで学芸員たちの工夫を展示してみました。
身近にある100均グッズを活用して、自然観察を道具作りの工夫から楽しんでしまいましょう。
場所:大阪市立自然史博物館本館 2F イベントスペース
展示期間:9月29日~11月11日
主催:大阪市立自然史博物館・西日本自然史系博物館ネットワーク
自然史系学芸員100円グッズプロジェクトについては
https://museum.bunmori.tokushima.jp/ogawa/100yen/index.shtml
を御覧ください

当日参加いただいた皆さん。
展示製作WSの様子をホームページに掲載しました。
https://museum.bunmori.tokushima.jp/ogawa/100yen/2012osaka/index.shtml