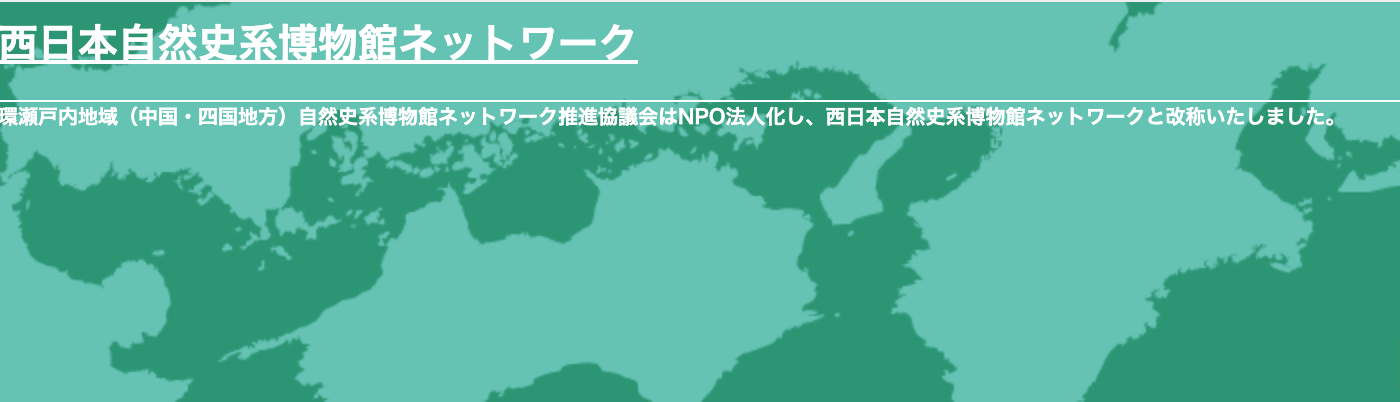定款(2014年改正)
法改正に伴い、定款を若干修正いたしました。(事務局)
特定非営利活動法人西日本自然史系博物館ネットワーク 定款
第1章 総則
(名称)
第1条
本法人の名称は特定非営利活動法人西日本自然史系博物館ネットワークとする。
(事務所)
第2条
本法人の事務所は大阪市東住吉区長居公園1番23号に置く。
(目的)
第3条
本法人は、21世紀の日本における自然史系博物館が社会に果たすべき役割の重要性と潜在的可能性を再認識し、自然史系博物館を活用した市民学習の支援、自然科学の振興、自然環境管理に必要な基礎情報の収集と研究、博物館と諸機関・諸団体との広汎な連携の構築といった諸課題を推進するとともに、併せてまちづくり、国際交流及び情報化社会の発展にも寄与することを目的とする。また、これらを実現するため、博物館関係者および市民による活動を支援し、経験と成果を蓄積する。
(特定非営利活動の種類)
第4条
本法人は、前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法 第2条別表
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4) 環境の保全を図る活動
(5) 国際協力の活動
(6) 子どもの健全育成を図る活動
(7) 情報化社会の発展を図る活動
(8) 科学技術の振興を図る活動
(9) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
を行なう。
(事業)
第5条
本法人は上記の目的を達成するために以下の事業を特定非営利活動に関わる事業として行なう。
(1) 博物館連携推進事業
地域の自然学習の中核施設である博物館の諸活動を支援するために、参加館園やNPO、都道府県や諸官庁と協力して、展示や学習資料の開発、教育普及プログラムの開発など、教育普及活動および必要な研究活動を支援し、必要に応じ事業を受託する。
(2) 地域自然環境情報提供事業
事業参加する館園の協力を得てデータベースの協調動作を維持し、インターネットにより地理情報システムの公開を行なう。また、このシステムの改善や支援プログラムの開発などを行なうとともに、必要な普及活動などを行なう。また、このために必要な各種事業を受託する。
(3) 調査研究推進事業
本法人は、自然史科学の普及に寄与するため、また博物館の活用を促進し、博物館事業および学芸員の資質を向上するため、参加組織および内外の博物館の学芸員の経験交流を行なう。またこれらに関わる受託研究・調査を企画し、国内・国際組織と連携を図り、そのために必要な事業受託を行なう。
(4) 普及事業
本法人は、自然史科学の普及に寄与するため、また博物館の活用を促進するためシンポジウム・セミナーの開催など必要な諸活動を行なう。またそのために必要な事業受託を行なう。
(5) 出版事業
本法人は、自然史科学および博物館活動の普及のために必要な書籍等を出版する。
(6) 展示企画事業
本法人は、自然史科学および博物館活動の普及のために必要な展示を博物館などと共同で企画し、実施する。またそのために必要な事業受託を行なう。
(7) その他
本法人の目的の達成に必要と認められる上記以外の事業を実施する。
第2章 会員
(種別)
第6条
本法人の会員は次の3種とし、正会員をもって法人における社員とする。
(1) 博物館会員
組織参加する自然史系博物館、ただし館長またはそれに準ずる学芸職員が正会員として登録されていること
(2) 正会員
本法人の趣旨に賛同する個人
(3) 賛助会員
本法人の事業を賛助する個人又は団体
(入会)
第7条
本法人に入会しようとする者は、理事長あてに申し込む。理事長は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
2 理事長は、入会を認めないときには、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知する。
(会費)
第8条
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(資格の喪失)
第9条
会員は、理事会において別に定める書式を理事長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員は、次の事由により資格を喪失する。
(1) 会費を3年以上滞納したとき
(2) 本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 除名されたとき
(除名)
第10条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決に基づき除名することができる。
(1) この定款に違反したとき
(2) 本法人の秩序を著しく害し、又は、公序良俗に反する行為をしたとき
(3) 本法人の目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第11条
会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
第3章 役員
(役員の種類及び定数)
第12条
本法人には次の役員を置く。
(1) 理事 4〜10名。うち1名を理事長、2名以内を副理事長とする。
(2) 監事 1名以上2名以内
(役員の選任)
第13条
役員は、総会において社員の中から選任する。
2 監事は、理事又は本法人の職員を兼ねてはならない。
3 理事の中からその互選によって、理事長並びに副理事長を選任する。
(理事の職務)
第14条
理事長は本法人を代表し、その業務を統括する。
2 理事長以外の理事は、本法人の業務について本法人を代表しない。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、理事長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
4 理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び総会の議決に基づき、本法人の業務の執行を決定する。
(監事の職務)
第15条
監事は次の業務を行なうものとし、その執行に当たって必要なときは随時理事に対して報告を求め、調査することができる。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) 本法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、本法人業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること
(5) 1号、2号の点について理事に個別に意見を述べ、必要により理事会を招集すること
(役員の任期及び欠員補充)
第16条
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。
4 理事が最低人数を下回ったとき、又は監事が不在となったときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(資格の喪失及び解任)
第17条
役員が死亡したときはその資格を喪失する。また、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で総会において出席者の3分の2以上の決議に基づいて解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反があると認められるとき
(3) その他役員として相応しくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第18条
役員は無報酬とする。
2 役員には、その業務遂行に必要な費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は理事会において別に定める。
(顧問・各種委員会)
第19条
本法人は、理事会の決議により、顧問および各種委員会を置くことができる。
2 顧問および各種委員会委員は、理事長の諮問に応じて助言を行ない、または理事会の要請があるときは、これに出席して意見を述べることができる。
3 顧問および各種委員会に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第4章 総会
(総会の構成)
第20条
総会は、本法人の最高の意思決定機関であって、社員をもって構成する。
2 賛助会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
3 総会は、定期総会と臨時総会とする。
(総会の機能)
第21条
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務
(7) 会費の額
(8) 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第22条
定期総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 社員の総数の6分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき
(3) 第15条第4号の規定に基づき、監事からの招集があったとき
(総会の招集)
第23条
総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、及び審議事項を記載した書面、又は電磁的方法をもって、すくなくとも14日前までに社員に対して通知しなければならない。
(総会の議長)
第24条
総会の議長は、その総会において、出席社員の中から選出する。
(総会の定足数)
第25条
総会は、この定款に他に定めがない限り社員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(総会の議決)
第26条
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席社員の過半数をもって決す。
(総会における書面表決等)
第27条
やむを得ない理由のために総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面、又は電磁的方法をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、出席したものと見なす。
(会議の議事録)
第28条
総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)出席した正会員の数(書面、又は電磁的方法による表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印した上、この議事録を本法人の事務所において5年間備え置く。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第29条
理事会は理事をもって構成する。
2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第30条
理事会は、第15条第5号の規定により監事が招集する場合を除き、年度2回以上、理事長が招集する。
2 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事長が理事会を招集するときは、会議に付議すべき事項並びに日時及び場所を示して、開催日の1週間前までに、理事に対し、書面、又は電磁的方法をもって通知しなければならない。但し、全理事の同意があるときは、この手続きを経ずして開催することができる。
4 監事が第15条第5号により理事会を招集するときは前項を準用する。
(理事会の議事)
第31条
理事会の議長は理事の中から互選する。
2 理事会においては理事現在数の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数をもって決する。
4 理事会の議事については、事務局において議事録を作成する。署名人は当該理事会において2名を選定する。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第32条
本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 寄付金品及び助成金
(3) 会費
(4) 事業に伴う収益
(5) 財産から生ずる収益
(6) その他の収益
(資産の管理)
第33条
本法人の資産は理事会の議決を経て理事長が管理する。
2 本法人の経費は資産をもって支弁する。
(活動予算及び決算)
第34条
本法人の事業計画及び活動予算は、総会で決定する。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず事業年度開始までに、活動予算が決定されないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算を基準として執行することができる。
3 前項による収益費用は、成立した予算の収益費用とみなす。
4 活動決算は事業年度終了後3ヵ月以内に、事業報告、財産目録、貸借対照表及び活動計算書とともに、監事の監査を受け、監査報告書を添えて総会の承認を得なければならない。
5 会計の決算上、剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
(予備費の設定及び使用)
第35条
前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の費用に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経ねばならない。
(事業年度)
第36条
本法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり当年12月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条
この定款を変更するときは、総会に出席した社員の4分の3以上の多数の議決を経、かつ法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第38条
本法人は、法令の規定による場合に解散する。この場合総会の決議によるときは、社員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。
第8章 事務局
(事務局の設置)
第39条
本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には所要の職員を置くことができる。
3 職員は理事長が任免する。
4 理事は職員を兼職することができる。
5 理事会の議決により、事務局業務の一部を外部に委託する事ができる。
6 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
(備付け書類)
第40条
事務局は事務所において、定款、その認証及び登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。
2 事務局は毎事業年度初めの3ヵ月以内に、前年度における下記の書類を作成し、これらを、その翌々事業年度の末日までの間、事務所に備え置かなければならない。
(1) 前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び活動計算書
(2) 役員名簿(前事業年度において役員であったことのあるもの全員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿)
(3) 前号の役員名簿に記載された者のうち前事業年度において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面
(4) 前事業年度において正会員であった10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面
(閲覧)
第41条
会員及び利害関係人から前条の備え付け書類の閲覧請求があったときは、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
第9章 雑則
(公告)
第42条
本法人の公告は事務所に掲示する他、官報においてこれを行なう。
(委任)
第43条
この定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
付則
1 この定款は、本法人の成立の日から施行する。
2 本法人の設立当初の役員並びにその役職は、第13条第1項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第16条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 本法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第34条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 本法人の設立初年度の事業年度は、第36条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年12月31日までとする。
5 本法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
博物館会員 0円
正会員 年額 1,000円
賛助会員 年額 一口10,000円