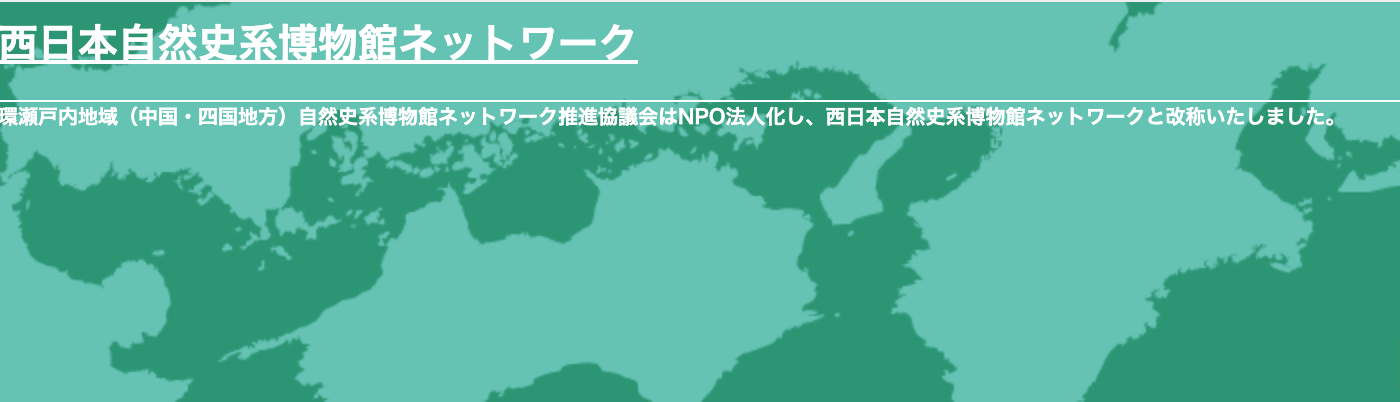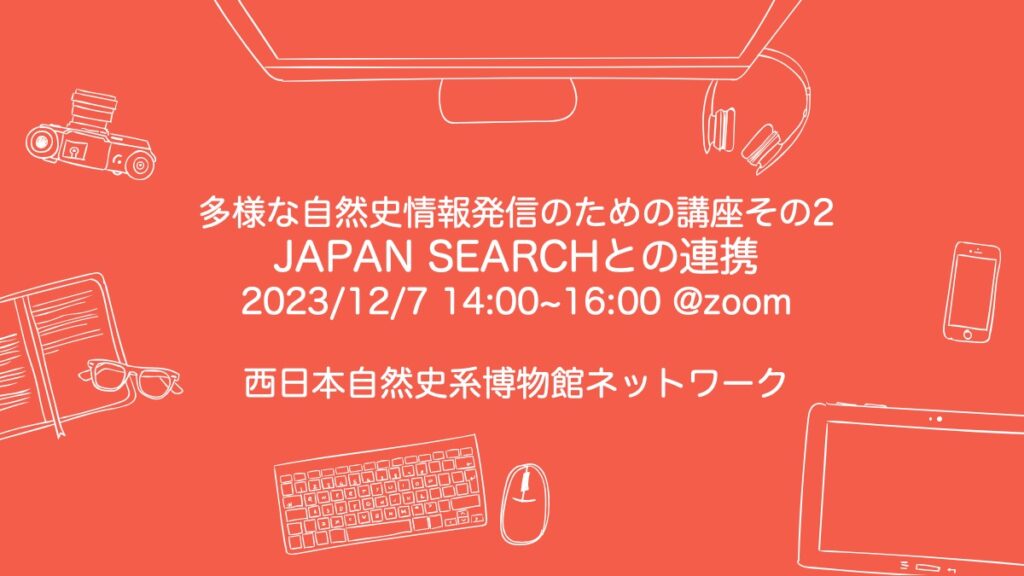西日本自然史系博物館ネットワーク総会・シンポジウム
表題の通り西日本自然史系博物館ネットワーク総会を
2025年2月3日月曜 13時から大阪市立自然史博物館にて行います
なお当日は
総会終了後の14時30分からシンポジウム
「自然史博物館の資料と保存 〜コレクションの保全を視野に」
を開催します。
■■西日本自然史系博物館ネットワーク総会は定足数があります。
Zoom参加の方も必ず以下から登録ください。
欠席の場合はお手数でも委任状をお送りください■■
記
西日本自然史系博物館ネットワーク2025年総会
議題
1 2024年度事業報告およびInnovateMuseum事業中間報告
2 2024年度収支決算
3 2024年度監査報告
4 2025、2026年度事業計画
5 2025、2026年度収支予算
6 2025年度の事務局体制について
7 その他
日 時:2025年2月3日(月)午後1時~
会 場:大阪市立自然史博物館またはオンライン会議システム(zoom)
●現地参加の方:当日は休館日となります。大阪市立自然史博物館事務所入口からお越しください。
●Zoom参加の方:以下から事前登録ください
このミーティングに事前登録する:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/ew2hlBvJQo6po_7s7yeH0g
登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。
●欠席の方:以下の委任状をnaturemuseumnet@gmail.comへお送りください
============================================
特定非営利活動法人 西日本自然史系博物館ネットワーク 御中
私は、 氏を代理人と定め、2025(令和7)年2月3日開催の特定非営利活動法人西日本自然史系博物館ネットワークの総会の議決権を行使する権限を委任します。
年 月 日
住所
氏名
============================================
シンポジウム
「自然史博物館の資料と保存 〜コレクションの保全を視野に」
西日本自然史系博物館ネットワークは、自然史博物館に関わる専門家集団として、自然史資料の保全に重大な関心を持っています。この度、三橋弘宗・高野温子編による『自然史博物館の資料と保存』の出版を機会に、わたしたちの原点である資料の保存管理に焦点を与え、技術面だけでなく社会的な情勢まで含めて議論をしたいと思います。
日時:2025年2月3日14時30分〜16時30分ごろ
場所:大阪市立自然史博物館・オンライン
プログラム概要
●『自然史博物館の資料と保存』の出版記念座談会
高野温子・奥山清市・矢部 淳・林 光武 ほか
●コレクションの保存と管理を視野にSPNHCから岩田コレクションまで
佐久間大輔・松井淳ほか
申込不要
現地参加の場合:大阪市立自然史博物館 集会室 事務所入口からお越しください
オンラインの場合:大阪市立自然史博物館YouTubeチャンネルより御覧ください。(見逃し配信あり)
*このシンポジウムはInnovate Museum事業の一環として開催します。